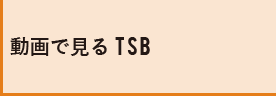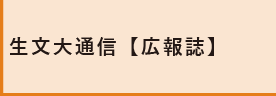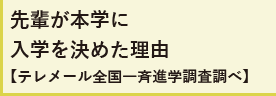本日令和7年4月4日(金)、本学の入学式が行われました。
大学短大の新入生と編入生が一堂に会し、これからの学生生活に向けて新たな一歩を踏み出しました。
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます!

令和7年度入学式 学長式辞
久方ぶりに太陽が顔を出し、春の訪れを感じさせる今日を迎えることができました。虹ヶ丘キャンパスの入り口にある紅梅、白梅も美しい姿を見せておりましたが、まもなく、三島学園に咲き誇る桜花がところせましと満開を迎えます。
本日は御来賓、保護者の皆さんに、多数ご列席いただき、令和七年度入学式が無事挙行されることとなりました。
東北生活文化大学、ならびに東北生活文化大学短期大学部を代表いたしまして、皆さんに御入学のお祝いを申し上げます。ともに、今日を待ち望んでおられた保護者の皆様に対しましても、衷心よりお祝い申し上げます。
もともと「いはふ」という言葉は、魂を鎮めるために精進潔斎を表す言葉だそうです。近代では、幸福な光り輝く現状を讃美し、将来もかくあるべしと、幸せな状況をみんなで喜び合う意味になったのだと、言われております。
栄えある今日を迎えた新入生は、東北生活文化大学 家政学部家政学科服飾文化専攻 16名、同健康栄養学専攻 41名、美術学部美術表現学科 55名、の計112名であります。
東北生活文化大学短期大学部 生活文化学科食物栄養学専攻 20名、同子ども生活専攻12名、の計32名。大学、短期大学部、 合計144名であります。
東北生活文化大学家政学部家政学科健康栄養学専攻第三年次への編入学は、3名であります。
三島学園東北生活文化大学、ならびに短期大学部の歴史を紐解くと、明治33(1900)年、東京で法学を学んだ三島駒治が、「東北法律学校」を設立、続いて三島駒治、よし夫妻によって創設された「東北女子職業学校」にまで遡(さかのぼ)ります。衣食住という「生活と文化」を基軸に据え、現実の社会生活に貢献しうる「実学」を重視する教育研究機関として、明治、大正、昭和、平成、そして令和と、東北における日本社会の近代化の一翼を担ってきました。本学は、生活することの原理、原初に立ち返り、学科、実験、実習、実技授業を重ね、実証していくという教育研究の姿勢を貫いております。いわば、『学問のすゝめ』で福沢諭吉が語る「サイエンスとしての実学」を、ICT(情報通信技術)をも活用して、実践していると言えないでしょうか。
来週、4月7日月曜日2時30分からこの体育館にて、ウェルカム・パーティーが開催され、新入生をお迎えし、おもてなしをする機会があります。主催する先輩学生たちから聞いたのですが、いろいろと趣向を凝らし、楽しい会にしたいとのことでした。
虹の丘に集うこの共同体が、修学に勤しむ(いそ)日々を全うするには、当然のことながら、ハレとなる「祭り」が欠かせません。このような晴(はれ)と褻(け)が交差するバイオリズムが奏でる大きなうねりによって、日々の生活が活性化するのです。季節が移り変わる節目に、体育祭、七夕祭、大学祭、クリスマス・パーティーが開催されております。わたくし学友会会長としても、新入生の皆さんに是非参加していただきたいと思っています。
新入生の皆さんと同年齢の時、わたくしはどうだったのか。不安に苛まれ、「自分とはなにか」「これからどのように生きて行くのか」と、当てどなく思案していました。縁側に寝そべって、朦朧とする月の姿を眺めると、そこにはるかに遠い、行方も知らない、曇った心の乱れを感じていたのかもしれません。
そのような時期、絵を描くことが唯一の楽しみでした。線を引く、色を塗るという行為が楽しい。画面のなかの、その線と色とを見ていると、心が少し晴れてくるのです。筆を動かすと、次の一手のアイディアが生まれ、線が加えられ、色も加えられる。目を媒介としての対象物と画面との往還は、手の運動によって繰り返され、知らず知らずのうちに、画面は進展します。そこには、自意識によるコントロールではない、無意識の心身の働きがあるようです。そうすることによって、自分自身を取り戻していたようです。
新入生の皆さん、この四季溢れる東北生活文化大学、東北生活文化大学短期大学部で修学に励み、楽しく友と語らう学生生活を過ごしていただきたいのです。教員、職員、そして、助手、副手の方々とのコニュニケーションにもきっと勇気づけられます。そうこうしているうちに、修学、制作を通して、心の奥深くに宿る本来の真の「自分自身、自己」の姿を、ふと自覚できる瞬間がきっととあることでしょう。そうなりますと、個人としての主体性が発揮でき、身近に友達もできます。ひいては、人生百年時代の楽しみや自由を享受できるのではないでしょうか。
このような自己実現を一人ひとりが実践しますと、東北、仙台の「生活と文化」が、多様性に満ちたエネルギーの束となって生み出されます。
現代は、「グローバルな地球社会」と「ローカルな地域社会」が組み合い、結びつかなければなりません。その理想的な形を実現すべく、新入生の皆さんをはじめ、若人の活躍する21世紀があると確信しております。
教職員、同窓生一同、皆さんの御入学を心からお祝いし、近未来の生活の幸せをつかむために学園生活を通して、「励(はげ)み、謹(つつし)み、慈(いつくし)み」、そして「地球社会」および「地域社会」の一員として成長なさることを祈念し、式辞といたします。
令和7年4月4日
東北生活文化大学・東北生活文化大学短期大学部
学長 佐藤一郎